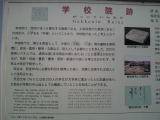更新日:
あなたは

番目の訪問者です
(ogino作成共通カウント)
★
旅と歴史ホームページ
OGIさんのHP
信州上田ホームページ
信州長野ホームページ
真田一族のホームページ
Mr.ogino旅ホームページ
上田の旅と歴史HP
信州の旅HP
日本の旅
世界の旅HP
★
|
門司港駅
もじこうえき
福岡県北九州市門司区港町

 |
門司港駅は、大正3年(1914)にローマのテルミネ駅を模して建てられた駅舎です。九州で最も古い木造の駅舎で、駅としては全国で唯一国の重要文化財に指定されています。 |
| 木造2階建ての本格的なフレンチ・ルネッサンス様式を用い、左右の造りが対称的な美しさを出しています。 |
 |
 |
大理石とタイルの洗面所、1階トイレにある青銅製の手水鉢などは、門司駅開設当時からのものです。手水鉢は、戦時中の貴金属供出から免れたことから、幸運の手水鉢と呼ばれているそうです。 |
旧門司三井倶楽部
きゅうもじみついくらぶ
福岡県北九州市門司区港町7ー1
Tel 093-321-1199

 |
旧門司三井倶楽部は山あいの門司区谷町より門司港レトロ地区に移築された建物です。この建物は門司港駅と並んで国の重要文化財に指定されています。 |
| この建物は大正10年(1921)、三井物産門司支店の社交クラブとして建築されました。建物はハーフティンバー様式(木骨様式)と呼ばれるヨーロッパ伝統の木造建築工法で作られました。 |
 |
 |
昭和24年(1949)から国鉄の所有となり、「門鉄会館」として利用され、 昭和62年(1987)、国鉄清算事業団に移管、その後北九州市に無償譲渡されました。 |
| アインシュタインが大正11年(1922)に宿泊した2階の部屋が当時の状態保存され「アインシュタインメモリアルルーム」として展示されています。また、門司区出身の林芙美子にちなみ、林芙美子資料室もあります。 |
 |
国際友好記念図書館
福岡県北九州市門司区東港町1ー12
Tel 093-331-5446

 |
明治35年(1902)に大連市に帝政ロシアがドイツ系ハーフテンバー様式により建てた建築物を、北九州市・大連市友好都市終結15周年を記念して複製建築されたものです。 |
| 1階のエントランスホールには、大連市、仁川市を紹介するビデオコーナー、2階は中国を中心とする東アジアの文献・資料などを収蔵した図書館、3階には大連市のか、友好・姉妹都市に関する資料展示コーナーがあります。 |
 |
旧門司税関
きゅうもじぜいかん
福岡県北九州市門司区東港町1ー24

 |
旧門司税関は、2代目の門司税関庁舎として明治45年(1912)に建てられ、 昭和2年(1927)まで使用されていたそうです。門司レトロ開発の一環として北九州市が買い取り、平成6年(1994)に修復されました。今はレトロ地区の象徴ともいえる赤煉瓦の建物です。 |
| 大蔵省臨時建築部にいた妻木頼黄と咲寿栄一が設計したそうです。他にも数多くの官庁建築を手がけています。この旧門司税関は、1階は休憩室・展示室があり、2階は展望室になっています。そこからは市街地や海峡を一望できます。 |
 |
旧大阪商船
きゅうおおさかしょうせん
福岡県北九州市門司区港町7−18
Tel 093-321-4151

 |
旧大阪商船は門司港レトロ地区にあります。大阪商船の門司支店として、大正6年(1917)に建設されました。 |
| 昭和39年(1964)、大阪商船と三井船舶が合併し、商船三井ビルと呼ばれ、平成2年まで使用されていました。その後、北九州市が買い取り、平成11年(1999)、国の登録有形文化財に登録されました。 |
 |
 |
オレンジ色タイルと白い石の帯のレトロなデザイン、そして八角形の塔が特徴です。現在1階は海峡ロマンホール、2階は「わたせせいぞうと海のギャラリー」と門司港アート村ギャラリー「港のマチエール」になっています。 |
松本清張記念館
まつもとせいちょうきねんかん
福岡県北九州市小倉北区城内2ー3
Tel 093-582-2761

 |
松本清張記念館は小倉城の一角に平成10年(1998)にオープンしました。小倉生まれ、その半生を小倉で過ごした松本清張は、「点と線」がベストセラーになり社会派推理小説ブームを巻き起こしました。 |
| 書斎や3万冊にも及ぶ書庫などを再現し、清張文学や彼の生涯を、グラフィカルに分かりやすく展示紹介しています。 |
 |
小倉城
こくらじょう
福岡県北九州市小倉北区城内2ー1
Tel 093-561-1210

 |
小倉城は南北朝時代以後、大内氏、太宰少弐氏、大友氏、菊地氏ら有力大名の争奪の的となり、めまぐるしく城主は交代しました。 |
| 天正14年(1586)、九州平定の軍を進めた豊臣秀吉は毛利勝信に8万石を与えて小倉城主とし、勝信は小倉城の改築に着手しました。 |
 |
 |
慶長5年(1600)、関ケ原の合戦後、豊前一国と豊後二郡32万石で入封した細川忠興は中津城に入りました。中津は地の利が悪いため、慶長7年(1602)から5年の歳月をかけて小倉城の大修築をして五重六層の天守を築き上げました。 |
| 寛永9年(1632)、熊本の加藤忠広が改易になると、細川忠利は熊本に転封。播磨明石から小笠原忠真が15万石で小倉城主となりました。小笠原氏は九州探題として10代続き幕末を迎えました。 |
 |
 |
幕府の第二次長州征伐の時、小倉藩は奇襲攻撃をした長州軍に破れ、城を自ら焼き払って敗退しました。現在の天守は続櫓とともに昭和34年(1959)に再建されたものです。 |
八坂神社
やさかじんじゃ
福岡県北九州市小倉北区城内2ー2
Tel 093-561-0753

 |
八坂神社は小倉城内にあります。昭和9年(1934)に現在地へ移されたものです。もともとは城郭北西の鋳物師町に元和3年(1617)、細川忠興が小倉城の鎮守として創建したものです。 |
| 鷹狩に出た細川忠興が、小さな祇園社の祠の中のご神体を見ようと、扉をこじ開けようとしました。その時、中から一羽の鷹が飛び出し、忠興の目を蹴ったそうです。 |
 |
 |
目が見えなくなった忠興は、自分の行ないを恥じ、祠を立派な神社に建て替えさせました。すると、忠興の目は見えるようになったそうです。愛宕山の祇園社を南殿に、古船場町の祇園社を北殿とし、一つの大きな神社を造ったため、中では二つの祇園様が祀られています。 |
| 太鼓の祇園として親しまれ全国三大祇園の一つに数え上げられている小倉祇園祭は400年の歴史を持つ八坂神社の夏祭りです。映画「無法松の一生」で一躍有名になりました。 |
 |
森鴎外旧居
もりおうがいきゅうきょ
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目7ー2
Tel 093-531-1604

 |
明治の文豪森鴎外が旧陸軍第12師団軍医部長として小倉に勤務していた時の住居です。後に鴎外が書いた「鶏」は、この家を舞台にしたものだそうです。 |
| 鴎外は明治32年(1899)から2年10ヶ月間小倉に住んでいましたが、その最初の1年半住んだのが、この鍛冶町の家です。 |
 |
 |
そしてここで名訳とされるアンデルセンの「即興詩人」を翻訳し、「我をして九州の富人たらしめば」「鴎外漁史とは誰ぞ」などを書いたそうです。 |
宗像大社
むなかたたいしゃ
福岡県宗像市田島2331
Tel 0940-62-1311

 |
宗像大社(むなかたたいしゃ)は全国に六千余ある宗像神社の総本社で、沖津宮、中津宮、辺津宮の三宮を合わせた総称です。古くは「日本書紀」にその名が登場し、古来から海陸交通の守護神として崇敬を集めています。 |
| 沖津宮(おきつみや)は沖ノ島にあり、島全体が御神体となっていて、田心姫神 (たごりひめのかみ)を祀っています。沖ノ島は、現在でも女人禁制で、古代の遺跡が残っています。海の正倉院と呼ばれ出土品は国宝に指定されています。辺津宮神宝館で古代装飾品などを見ることができます。 |
 |
 |
中津宮(なかつみや)は筑前大島にあり湍津姫神 (たぎつひめのかみ)を祀っています。大島は神湊から海上8kmの地点にあります。沖ノ島は大島から48kmも離れています。 |
| 辺津宮(へつみや)は宗像市田島にあり市杵島姫神 (いちきしまひめのかみ)を祀っています。一般に宗像大社というと辺津宮のみを指す場合が多いようです。 |
 |
 |
三社に祭られている三柱は、宗像三女神(宗像三神)と総称されます。天照大神と素戔嗚尊の誓約(うけい)の際、天照大神の息から生まれたのが宗像三女神だということです。彼女達は天照の勅命を奉じ天孫を助けるため筑紫の宗像に降りこの地を治めるようになったといわれています。 |
| 鎌倉時代以降は武家の信奉もあり小早川、黒田氏などにより社殿の造修営、社領の寄進がなされました。辺津宮の本殿は天正6年(1578)、宗像大宮司氏貞が再建し、拝殿は天正18年、小早川隆景が造営しました。ともに国の重要文化財に指定されています。 |
 |
筥崎宮
はこざきぐう
福岡県福岡市東区箱崎1ー22ー1
Tel 092-641-7431

 |
筥崎宮は「筥崎八幡宮」とも称し、大分県宇佐市の宇佐神宮、京都府八幡市の石清水八幡宮とともに日本三大八幡宮に数え上げられています。応神天皇(八幡大神)と、その母である神功皇后、海の神様である玉依姫命を祀っています。 |
| 延喜21年(921)、醍醐天皇が国家鎮護のために建立したといわれ、博多区住吉の住吉神社とともに筑前国の一宮です。「敵国降伏」の震翰を掲げる桜門は伏敵門として有名です。 |
 |
 |
鎌倉中期、元寇の兵火で焼失しましたが、亀山上皇が社殿を造営して、建治元年(1275)紺紙に金泥で敵国降伏の4文字を37枚書いて奉納したそうです。 |
| 本殿は9間社流造りの桧皮葺き、拝殿は桁行4間、梁間1間、1重切妻造りの桧皮葺きです。天文15年(1546)、大内義隆により再建されたもので、国の重要文化財に指定されています。 |
 |
 |
「敵国降伏」の震翰を掲げてある楼門は3間1戸、入母屋造りの桧皮葺きです。建て坪は12坪ですが、屋根は83坪もあるそうです。文禄3年(1594)、小早川隆景に再建されたもので、国の重要文化財に指定されています。 |
香椎宮
かしいぐう
福岡県福岡市東区香椎4ー16ー1
Tel 092-681-1001

 |
香椎宮(かしいぐう)は仲哀天皇9年(200)、熊襲征伐の途中橿日宮(かしひのみや)で仲哀天皇が急逝され、神功皇后が祠を建て天皇の神霊を祀ったのが起源とされています。 |
| 養老7年(723)、神功皇后自身の御神託により朝廷が社殿の造営を始め、神亀元年(724)に竣工されたそうです。 |
 |
 |
古くから朝廷の崇敬厚く祈願・奉幣等は宇佐神宮に次ぐ扱いを受け、伊勢神宮、気比神宮、石清水八幡宮と共に「本朝四所」と称されました。 |
| 本殿は桁行3間、梁間3間、1重入母屋造りで正面と左右側面に破風付き、桧皮葺きの建物です。享和元年(1801)、藩主黒田斉清(なりきよ)の造営、修築と伝えられています。 |
 |
 |
香椎造とよばれる複雑な構造形式で国の重要文化財に指定されています。大伴家持は「いざ児等香椎の潟に白妙の袖さへぬれて朝菜つみてむ」と詠んでいます。 |
宇美八幡宮
うみはちまんぐう
福岡県粕屋郡(かすやぐん)宇美町宇美1ー1ー1
Tel 092-932-0044

 |
宇美八幡宮の創建は敏達天皇3年(575)で応神天皇、神功皇后、玉依姫命、住吉大神、伊弉冉尊(いざなぎのみこと)を祀っています。応神天皇が神功皇后から生まれた所でもあるのです。 |
| 神功皇后が三韓征伐中、仲哀(ちゅうあい)天皇との子を宿していました。ここ筑紫の国に戻って産んだ子が応神天皇で「宇美」の地名もこの時の「産み」に由来するものといわれています。 |
 |
 |
境内には、神功皇后が出産のときにすがりついたという「子安の木」、応神天皇の産湯に使ったと伝えられる「産湯の水」などがあります。 |
| 境内末社の湯方殿の前には「子安の石」と呼ばれる拳大の石が納められています。妊婦は安産を祈願してこの石を持ち帰り、出産後は別の新しい石を添えて返すという風習があります。 |
 |
 |
境内には湯蓋の森(ゆぶたのもり)という楠木と、衣掛の森(きぬかけのもり)といわれる楠木があります。両木とも国指定天然記念物となっています。これらの木は応神天皇降誕にまつわるご神木となっています。 |
大宰府政庁跡
だざいふせいちょうあと
福岡県太宰府市観世音寺4

 |
都府楼跡(とふろうあと)の名前で親しまれている大宰府政庁跡は奈良から平安時代にかけて九州一円を統轄していた役所大宰府があったところです。 |
| 7世紀後半、大和朝廷は那の津の官家(みやけ)をここに移し、九州を治め、わが国の西の守り(防衛)、外国との交渉の窓口となる役所(大宰府)としました。 |
 |
 |
太宰府は平城京、平安京に次ぐ大きな都市だったようです。万葉集には「遠の朝廷(みかど)」と詠まれました。しかし天慶3年(940)に藤原純友の乱で焼失してしまいました。 |
| 今は広い野原に立派な礎石が残り、往時をしのぶことができます。そこを中心に門や回廊、周辺の役所跡等が整備されて公園となっています。 |
 |
大宰府学校院跡
だざいふがっこういんあと
福岡県太宰府市観世音寺4ー208ー4

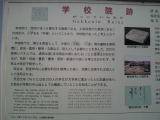 |
大宰府学校院は西国の役人を養成する機関でした。奈良時代、中央には大学、諸国には国学、大宰府には官吏養成のための学校院(学業院)がおかれました。明経・算・医の三学科がありそこでは九州一円の国司・郡司の子弟が学びました。 |
| 天応元年(781)には約200人の学生が大宰府に集まったとの記録があり、大宰府が学問の中心地としても機能していたことがわかります。 |
 |
戒壇院
かいだんいん
福岡県太宰府市観世音寺5ー6ー1

 |
戒壇院は聖武天皇の勅願により建立された観世音寺境内に天平宝字5年(761)に建てられた臨済宗のお寺です。奈良時代に出家者が正式の僧尼となるために必要な戒律を授けるために設置されました。 |
| 奈良の東大寺と下野(栃木県)の薬師寺とともに日本三戒壇の一つに数え上げられています。三大戒壇は唐の名僧鑑真和上を招き設置されました。鑑真和上が植えたといわれる菩提樹もあります。 |
 |
 |
中世に衰退しましたが、寛文9年(1669)、崇福寺 (福岡市)の智玄和尚によって本尊の修理が施され、黒田家の家臣鎌田昌勝によって再建されたそうです。元禄16年(1703)には観世音寺から独立しています。 |
| 平安末期作の毘廬舎那仏(るしゃなぶつ)座像が本尊であり、この本尊は国の重要文化財に指定されています。 |
 |
観世音寺
かんぜおんじ
福岡県太宰府市観世音寺5ー6ー1
Tel 092-922-1811

 |
観世音寺は天智天皇が母の斉明天皇の冥福を祈り、80年の歳月をかけて天平18年(746)に建立した勅願寺です。創建時には七堂伽藍を配した大寺院だったそうです。 |
| 大宰府政庁域の東に接して創建されていたので「府大寺」と称され、天平宝字5年(761)には境内に戒壇院が置かれ、西日本随一の寺院といわれたそうです。源氏物語にも登場し鎮西第一の巨刹と称されました。 |
 |
 |
現在は江戸時代初めに再建された講堂(本堂)と金堂(阿弥陀堂)のみが残るだけです。境内にある白鳳期の梵鐘(ぼんしょう)は、西暦681年に筑前国糟屋郡多々良で鋳造された日本最古の梵鐘で国宝に指定されています。京都・妙心寺の梵鐘と兄弟鐘といわれています。 |
| 鐘楼の裏手には「観世音寺宝蔵」があり平安時代から鎌倉時代にかけての仏像13体などが展示されています。これらはすべて国の重要文化財に指定されています。 |
 |
光明寺
こうみょうじ
福岡県太宰府市宰府2ー16ー1
Tel 092-922-4053

 |
神護山光明禅寺は臨済宗東福寺派のお寺で菅原家の一族出身の鉄牛円心和尚によって建立されました。苔寺の名で知られ枯山水の石庭は九州随一といわれています。 |
| 前庭の「仏光石庭」は15個の石を光の字型に配した庭で鎌倉期の紋砂山水様式を取り入れています。後庭の「一滴海庭」は青苔で陸を、白砂で大海を表現しています。 |
 |
大宰府天満宮
だざいふてんまんぐう
福岡県太宰府市宰府4ー7ー1
Tel 092-922-8225

 |
大宰府天満宮は京都の北野天満宮と並び、全国の天満宮の総本社といわれ、学問の神様、菅原道真を祀っています。「飛梅伝説」でも知られるように、境内には約6千本もの梅の木があります。 |
| 菅原道真は昌泰4年(901)に左大臣藤原時平らの陰謀によって筑前国の大宰府に権帥として左遷され、翌々延喜3年(903)に同地で亡くなります。翌年、安楽寺境内に味酒正行(うまさけのやすゆき)が廟を建てました。 |
 |
 |
都では疫病や異常気象など不吉な事が続き、道真の祟りと騒がれました。霊を鎮めるため、醍醐天皇は左大臣藤原仲平に大宰府に下向させました。そして道真の墓所の上に社殿を造営し、延喜19年(919)安楽寺天満宮が創建されたのでした。 |
| 明治に入り太宰府神社と名称が変わりましたが、昭和22年(1947)、太宰府天満宮になりました。受験合格や学業成就などを祈願する参拝客で、年中賑わい、初詣の際には九州はもとより日本全国から毎年200万人以上の参詣者がお参りしていきます。 |
 |
 |
現在の本殿は天正19年(1591)に小早川隆景が寄進したもので桃山時代の荘厳な造りの「五間社流造り」で国の重要文化財に指定されています。 |
| また長禄2年(1458)に建てられた末社志賀社本殿も国の重要文化財に指定されています。 |
 |
北野天満宮
きたのてんまんぐう
福岡県久留米市北野町中3267
Tel 0942-78-2140

 |
北野天満宮は天喜2年(1054)、後冷泉天皇の勅令により僧真仙(しんせん)が筑後河北に鎮祀した75社の一つで、京都北野天満宮の代官所として創建されたそうです。京都の北野天満宮の祭神である菅原道眞の分霊を祀っています。 |
| 源平の争乱で社殿は破壊されましたが、源頼義、頼朝によって社殿は再建されました。足利義満の代になると筑後一円を荘園として認められました。 |
 |
 |
戦国時代、兵火によって社殿は全焼しましたが、永正15年(1518)に草野重永が再興、天正15年(1587)に久留米城主毛利秀包(ひでかね)、慶長7年(1602)に久留米城主、田中吉政などが社領寄進しています。 |
| 天正15年(1587)、豊臣秀吉九州征伐の時、一時社領は没収されました。承応3年(1654)、久留米藩主有馬瓊林が社殿を改築し、ほぼ現在の天満宮の景観ができ上がりました。 |
 |
高良大社
こうらたいしゃ
福岡県久留米市御井町1
Tel 0942-43-4893

 |
高良大社は筑後国一の宮で、耳納(みのう)連山の最西端、標高312mの高良山にあります。天下の天下たるは高良の高良たるが故なりの言葉通り、鎮西筆頭の神社です。 |
| 履中天皇時代(319-409)の創建であるといわれ、延喜式神名帳には「高良玉垂命神社」と記載され、名神大社に列しています。 |
 |
 |
正殿に高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)、左殿に八幡大神(はちまんおおかみ)、 右殿に住吉大神の3柱の祭神を祀っています。高良玉垂命は国内最古の神名帳とされる「筑後国神名帳」によると、朝廷から正一位を授けられたとされています。 |
| 現在の社殿は、久留米藩3代藩主有馬頼利の寄進によるもので、万治3年(1660)に本殿が、寛文元年(1661)に幣殿・拝殿が完成しています。 |
 |
 |
本殿は江戸初期の権現造りで、正面から眺めると幅約17m、高さ13m、奥行き32mで神社建築としては九州最大の大きさを誇っています。 |
| 建立年次が明らかな社殿として貴重とされ、本殿、幣殿、拝殿は国の重要文化財に指定されています。また明暦元年(1655)、2代藩主忠頼(ただより)寄進の石造大鳥居も国の重要文化財に指定されています。 |
 |
善導寺
ぜんどうじ
福岡県久留米市善導寺町飯田550
Tel 0942-47-1006

 |
善導寺は昔は井上山光明寺と称し、浄土宗の開祖である法然上人の直弟子にあたる聖光上人(鎮西上人)が13世紀初頭に浄土宗寺院として開山した古刹です。 |
| 浄土宗の七大本山の一つで九州浄土宗の教化の拠点、念仏の根本道場となっています。善導寺という名は弁長の夢に、唐の善導大師(ぜんどうだいし)の告示があったので付けられたそうです。中国・唐の時代の名僧で、中国浄土教、殊に、曇鸞(どんらん)・道綽(どうしゃく)の思想の流れを大成した人といわれています。 |
 |
| 善導寺山門 |
 |
老木の茂る広大な境内には国の重要文化財に指定されている本堂が建っています。三祖堂、釈迦堂、薬師堂、観音堂、開山廟、鐘楼堂、山門、勅使門、大門、庫裏など江戸時代に建てられた諸堂が建ち並んでいます。 |
| 本堂 |
| 釈迦堂は山門の正面に建っています。すぐ脇には樹齢800年といわれる天然記念物の大楠が聳えています。聖光上人のお手植えと伝えられています。 |
 |
| 釈迦堂 |
 |
本堂のすぐ南に建つのが三祖堂です。その中央には、浄土宗開祖の法然大師、善導寺を開基した聖光上人を祀っています。 |
| 安産祈願所(三祖堂) |
風浪宮
(ふうろうぐう)
福岡県大川市酒見字宮内
Tel 0944-87-2154

 |
地元でおふろうさんと呼ばれている風浪宮(ふうろうぐう)は1800余年の由緒を持つ古社です。御祭神は少童命(わだつみのみこと)、息長垂姫命(おきながたらしひめのみこと=神功皇后)、住吉大神、高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)です。 |
| 神功皇后が三韓征伐からの帰途(192年頃)筑後国葦原ノ津(大川榎津)に寄った時、勝運を開いた少童命の化身の白鷺が忽然と現れたそうです。その白鷺が止まったクスのある所に社殿を建て少童命を祀ったのがはじまりです。 |
 |
 |
白鷺が止まったのが御神木でもある「白鷺の楠」で樹齢2千年といわれ、県の天然記念物に指定されています。 |
| 拝殿の脇には阿曇磯良丸(あづみいそらまる)の木像があります。少童命を祖神とする海の神とされ、神功皇后の三韓征伐において軍船の海上指揮をとるなどその成功に大きく貢献したそうです。 |
 |
 |
拝殿、本殿は戦国時代の筑後国柳川城主、蒲池鑑盛(かまちあきもり)によって永録3年(1560)に再建されたもので、国の重要文化財に指定されています。また境内にある石造五重塔も国の重要文化財に指定されています。 |
古賀政男記念館
こがまさおきねんかん
福岡県大川市大字三丸844
Tel 0944-86-4133

 |
古賀政男記念館は古賀政男の偉業をたたえ、これを永遠に記念するため昭和57年(1982)にオープンしました。影を慕いてなど4000曲にも及ぶ歌謡曲を残した大作曲家で、今も歌い継がれています。 |
| 中央部の白亜の塔と、ト音記号のレリーフが印象的な記念館で愛用のギター、マンドリン、大正琴、原譜などを展示しています。 |
 |
 |
小学校2年生まで住んでいたという生家も復元されています。 |
旧吉原家住宅
きゅうよしはらけじゅうたく
福岡県大川市小保136ー17
Tel 0944-86-8333

 |
旧吉原家住宅は、柳河藩小保町の別当職を代々務め、後には蒲池組の大庄屋となった吉原家の住宅です。屋敷は南面し、正面中央に御成門、右側に通用門を構えて堀を廻らしています。 |
| 式台玄関の蟇股に文政8年(1825)の墨書が残っており、当主吉原三郎左衛門三運により建築されました。巡見使の宿泊や藩の公用にも利用されたそうです。 |
 |
 |
旧吉原家住宅は、大規模で細部の意匠に優れ、建築年代も確実なものとして、国の重要文化財に指定されました。 |
筑後川昇開橋
ちくごがわしょうかいきょう
福岡県大川市大字向島
佐賀県佐賀市諸富町

 |
筑後川昇開橋は国鉄佐賀線の鉄道橋梁として建設され、昭和10年(1935)竣工、同年5月25日に開業しました。橋桁の一部が垂直方向に上下する昇開橋として日本に現存する最古のもので国の重要文化財に指定されています。 |
| 橋の全長は507m、中央部は高さ30mの2本の鉄塔に沿って23mの高さまで水平昇降をすることができます。開通当時は「東洋一の可動式鉄橋」と呼ばれ話題を呼んだそうです。 |
 |
 |
昭和62年(1987)3月、佐賀線の廃止とともに役目を終えました。筑後川のシンボルを存続させようと近隣住民の熱意が実り、平成8年(1996)遊歩道として蘇りました。 |
柳川城跡
やながわじょうせき
福岡県柳川市本城町

 |
柳川城は柳川藩主・立花氏10万9600石の居城でした。高い石垣と5層の天守閣を誇りましたが明治5年(1872)に焼失しました。石垣も明治7年(1874)の大風により海岸堤防決壊の際の補強に使ったためわずかしか残っていません。城跡は柳城中学校の校庭の一角の小高い丘とわずかな石垣の一部を残すのみです。 |
| 柳川城は永禄年中(1558-1569)、蒲池鑑盛(あきもり)によって本格的な城としてなりました。天正8年(1580)、龍造寺による数ヶ月に及ぶ攻撃に耐えましたが、謀略により翌年、応永以来の蒲池一族は滅亡しました。 |
 |
 |
天正15年(1587)、立花宗茂が豊臣秀吉の九州平定に際して、その功により城主になりました。関ヶ原役後、田中吉政が入封しましたが元和6年(1620)、吉政の子忠政に後継なく断絶。再び立花宗茂が治めることになり、以来明治維新を迎えるまで250年間立花藩の居城になりました。 |
北原白秋生家
福岡県柳川市沖端町55ー1
Tel 0944-73-8940

 |
代々海産物問屋だったという北原白秋生家には白秋の愛用品や著書などを展示しています。また白秋の幼少期の落書なども残されています。 |
| 白秋生誕百年にあたる昭和60年(1985)には敷地の一隅、裏庭に隣接して柳川市により北原白秋記念館(柳川市歴史民俗資料館)が開館しました。平成2年(1990)には母屋の下屋の書斎が復元されています。 |
 |
 |
北原白秋は明治・大正・昭和という時代を生きぬいた詩人です。「水郷柳川は、我詩歌の母体である」と述べ、57才で亡くなるまで生涯柳川を愛し、数多くのすぐれた詩を残しました。 |
御花 松濤園
おはな しょうとうえん
福岡県柳川市新外町1
TEL 0944-73-2189

 |
松濤園(しょうとうえん)は福岡県柳川市にある柳川藩主立花氏の別邸「御花」に設けられた日本庭園です。景観は松島を模したもので昭和53年(1978)に国の名勝に指定されています。 |
| 柳川藩主立花鑑虎が元禄10年(1697)普請方の田尻惟貞に命じ総面積約7千坪の集景亭という別邸を造らせました。この地が花畠という地名であった事から、柳川の人々から御花と呼ばれるようになったそうです。 |
 |
 |
立花家14代当主の立花寛治によって明治42年(1909)から2年にわたって新築された本館は、当時の宮家、富豪たちの間で流行った「西洋館の正面玄関に続く日本建築の大広間」という形式をそのまま残しています。 |
| 園内には約280本のクロマツ、1500の庭石、14の石灯籠があります。沓脱石の巨石は旧天守閣の台石を移したと言われています。池のなかの2つの島と多数の岩島および水面は、冬場には500羽もの飛来する野鴨の飛来地になっています。 |
 |
 旅と歴史のホームページへもどる 旅と歴史のホームページへもどる  日本のページへもどる 日本のページへもどる
|
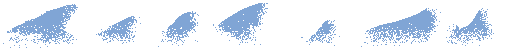





























 旅と歴史のホームページへもどる
旅と歴史のホームページへもどる  日本のページへもどる
日本のページへもどる